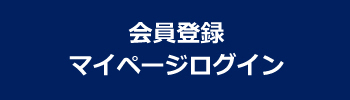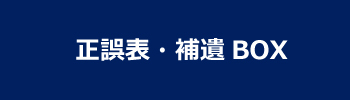月刊福祉(2023年5月号)
こども家庭庁が2023(令和5)年4月に発足。「こどもまんなか」社会に向けて、制度の拡充や子どもの目線に立った支援が広がることが期待される。一方で、長引くコロナ禍もあり子どもの育ちや学びへの影響が指摘され、不適切保育や虐待の問題等の子どもの権利を脅かす事象も続く。
こうした現状も踏まえ、2022(令和4)年5月号に続き、子どもを中心においた社会をつくっていくうえで、あるべき制度や支援のかたち、求められる支援者の姿勢等について確認する。
「こどもまんなか」とは何か―子どもの権利を守る視点から
くれたけ法律事務所 弁護士 磯谷 文明
社会福祉法人みその児童福祉会 岡山聖園子供の家 施設長、本誌編集委員〔聞き手〕 則武 直美
▼論点Ⅰ
相談支援を充実させる―島田市版ネウボラの取り組み
島田市健康づくり課 技監 鈴木 仁枝
▼論点Ⅱ
子どもの意見を聴き、くみ取る
特定非営利活動法人Giving Tree ピアカウンセラー 畑山 麗衣
▼論点Ⅲ
地域における児童養護施設等の新たな役割
社会福祉法人子供の家 児童養護施設子供の家 施設長 早川 悟司
▼論点Ⅳ
18歳以降を支援する―「子ども」のその後とは
名古屋市立大学大学院人間文化研究科 准教授 谷口 由希子
▼論点Ⅴ
これまでと、これからの家族政策
東京経済大学経済学部 教授 李 蓮花
▼てい談
子どもに向き合う支援者に求められること
社会福祉法人愛育会 認定こども園あけぼの愛育保育園 園長 北野 久美
社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 施設長 都留 和光
朝日新聞 編集委員〔進行兼〕 大久保 真紀
【グラフ21】
社会的養護等経験者全国交流会
若者たちの思いとリアルな声を世の中へ
【ウオッチング2023】
福祉ジャーナリスト、元NHKアナウンサー 町永 俊雄さん
小さな声を積み重ねた先に福祉が見えてくる
創刊1909(明治42)年。100年を超える伝統と歴史――
『月刊福祉』は、最新の福祉政策・動向をお届けする信頼と実績の福祉の総合誌です。
― 変化する社会保障・社会福祉制度の動向や課題を整理
― 多様な福祉課題への対応を、実践事例を交えながら多角的に紹介
― 福祉関係者はもちろん、福祉の今を知りたい方々にもお読みいただきたい1冊
【注目の連載】
▼FUKUSHIを創る
ニーズや社会・地域課題を前にし、それに対応するため、新たな発想や視点をもとにこれまでにない実践に取り組んだ中心人物に焦点を当てるコーナーです。
▼ありのままの自分を―当事者の思い さまざまな当事者の想いや日々の暮らしの状況について、本人や寄り添う身近な人の視点から語り、当事者への理解を深めます。
▼知っておきたい福祉の基礎知識
福祉の主要な制度や仕組み、支援技術や対象、機関等に関するテーマを、毎号ひとつ取り上げます。新任者にとっては学びの入口となり、経験者にとっては忘れてはいけない基本事項を改めて確認できるコーナーです。
≪このような方におすすめします≫
●今、知っておきたいテーマを第一線の学識者や実践者の解説から学びたい方
●今の福祉を多角的な視点から押さえて経営・運営に活かしたい社会福祉法人・福祉施設の経営管理者の方、この先の組織の中核を担っていく方
●社会福祉を研究する方、社会福祉を学ぶ学生の方、福祉の最前線で活躍する法人・施設職員の方
…毎日を有意義に過ごすためのヒントが『月刊福祉』には詰まっています。
特集一覧
- 2024年5月号特集 真に子どもの声を聴く、その先にある社会
- 2024年4月号特集 報酬改定から見通すこれからの社会保障
- 2024年3月号特集 「共に生きる力」を育む
- 2024年2月号特集 第三者の視点を入れる、利用者の声を聞く
- 2024年1月号特集 人材確保の未来を考える
- 2023年12月号特集 外国人とともに「福祉」で働く
- 2023年11月号特集 デジタルでつながる福祉
- 2023年10月号特集 2040年を見据えた高齢者支援のこれから
- 2023年9月号特集 福祉と人権 ―利用者と職員の人権を守るために
- 2023年8月号特集 市町村社協を知る - これからも地域福祉の中核であり続けるために
- 2023年7月号特集 生活保護と生活困窮者自立支援の方向性
- 2023年6月号特集 誰もが当たり前に一緒にいる地域の場
ご注文
1,068円(税込)